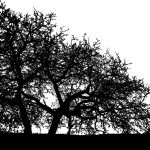あん福祉会などのグループホームは日本において高齢者、あるいは障がい者を対象に提供される施設で、家族を離れて同じような境遇の人達と一緒に生活をするのが特徴です。
元々はヨーロッパの障がい者解放運動にルーツがあるとされており、健常者も障がい者も同じように生活できる社会を目指す、いわゆるノーマライゼーションから生まれました。
ヨーロッパにおいては精神的、知的障がい者が隔離施設から解放され、その行き先としてグループホームが用意されました。
そこでは支援を受けながら少人数が共同で生活を送り、社会に溶け込む形で存在しています。
関連記事:あん福祉会のスタッフ募集について
一般的な福祉施設との違い
最初は精神疾患を抱える人向けでしたが、やがて対象者が知的な障がい者にも拡大しました。
一般的な福祉施設と異なるのは、あくまでも住宅の一種で、生活様式が共同生活となっている点です。
18世紀頃に誕生した当時のグループホームは、アパートだったりホームステイするタイプ等様々が造られ、100床以上の大規模な施設もあったようです。
現在のように、認知症の高齢者を対象とした施設が誕生し始めたのは1980年代のことで、スウェーデンにおいて認知症患者ケアの取り組みが始められたのが最初といわれています。
民家を借りる形で取り組みが行われたこのケースは、認知症の高齢者が共同生活を行う初めての事例となりました。
日本における高齢者向けのグループホームも、実はこのスウェーデンの事例を参考にしています。
日本で広くこのような施設が知られるようになったのは、2000年度に合わせて当時の厚生省がゴールドプラン21を計画したのが切っ掛けです。
ゴールドプラン21とは来る高齢化社会に備える高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略の通称で、1989年に策定された最初のゴールドプラン、1995年の新ゴールドプランに続くものです。
健康的かつ生きがいを持って参加できる社会を念頭に、介護サービスの受けやすさや高齢者が尊厳を保てる社会作り、そしてサービスを提供する施設の拡充が盛り込まれました。
この制度の施行によって介護関連の施設は一気に広まり、全国的に増加することになります。
日本では現在も認知症の高齢者が主な利用者ですが、自治体によっては独自に知的障がい者を対象とした条例を制定したり、施設を拡充しているところもあります。
利用者本人や家族が探して入居することが必要
このように、国の取り組みで普及拡大や定着が行われたグループホームですが、利用者本人や家族が探して入居することが必要です。
理由は自治体の介護課、社会福祉協議会は仲介することができないからです。
その一方で、介護保険のように安心して利用できる制度が存在しているのも確かです。
日本の介護保険は社会で要介護者とその家族を支える仕組みで、要介護認定を受けると入居することが認められます。
逆にいうと要介護認定を受けていなかったり、認定の対象外の人は利用できないことを意味します。
要支援の人は基本的に利用できませんが、介護予防の指定を受けている事業所であれば利用可能です。
要支援1だと事業所を問わず利用の対象外ですから、施設に入居して共同生活を送ることはできないです。
反対に、要介護認定なら入居の対象なので、介護保険を利用して施設に入ることができます。
こういった認知症高齢者向けの施設は既に全国で5千を超えており、いかに高齢化が進んでいるか、認知症が他人事ではなく社会の問題かということが分かります。
しかし、障がい者を隔離するのではなく同じ社会で健常者と一緒に暮らす環境を目指した結果なので、このように住み分ける施設の存在は不可欠です。
日本の介護保険付きサービスの分類
日本の介護保険付きサービスは居宅型と地域密着型、施設型に分けることができます。
居宅型は通所や短期的に入所するタイプの施設で、全体の半数くらいを占める規模を誇ります。
つまり、大半はこの居宅型を利用しており、訪問して入浴の介護を受けたりリハビリを受けているわけです。
地域密着型は小規模な多機能型居宅介護や認知症向けの施設で、割合的にはそれほど多くないです。
施設型は特養や老健で知られる、介護福祉施設や介護老人保健施設が大半です。
認知症グループホームは地域密着型に分類されるので、小規模多機能型居宅介護や地域密着型介護老人福祉施設と同じカテゴリに入ります。
給付は500億円超にのぼり、介護保険サービス給付全体の5%以上を占めています。
認知症の高齢者を対象にサービスを提供する施設ですから、介護職員の負担の大きさや、過酷な勤務に対して給与が低いといった問題が度々話題になります。
それと、過去には火災が発生したことで被害が拡大したことから、防火管理業務の義務付け条件が厳しくなったり、消防用設備等の義務付けが徹底されるようになっています。
まとめ
限られた介護職員で、認知症を抱える高齢者を速やかに避難させることは非現実的ですし、ましてや自力で避難してもらうのは不可能です。
その為、法的なルールが厳しくなるのは仕方がありませんし、必然的で厳しい現実が反映されているともいえます。
最終更新日 2025年4月25日