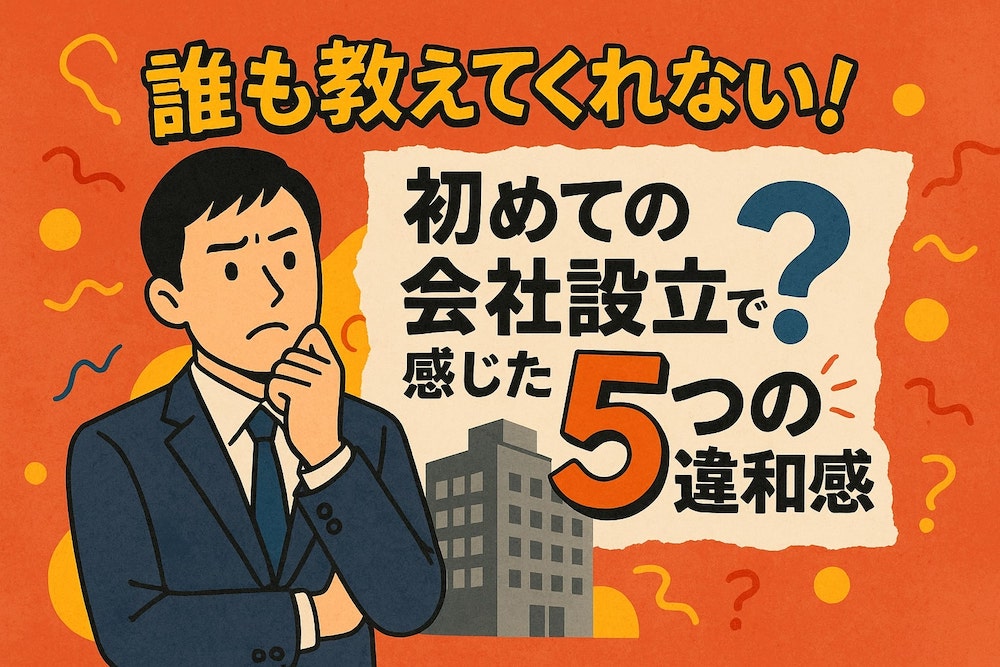私が初めて会社設立の書類に印鑑を押したのは、20年以上も企業支援に携わってきた後のことだった。
長年、誰かの起業を支援する側に立ち、「成功の秘訣」を語っていた私が、ある日突然、自分自身の会社を立ち上げることになったのだ。
仲間3人と始めた小さな合同会社。
実は、これが私の人生における最大の「違和感」との出会いだった。
支援する側から、される側へ——その視点の転換は、長年の経験をもってしても予測できない感覚をもたらした。
本記事では、起業支援のプロが自ら会社設立を経験して初めて気づいた5つの「違和感」をお伝えしたい。
これから会社を設立しようとしている方、あるいは設立したばかりの方が、事前に知っておくべき「教科書には載っていない現実」である。
「登記すれば会社」は幻想だった
書類の整備だけでは足りない”設立の実感”
会社設立において、登記は最も重要な法的手続きだ。
しかし、いざ自分が設立者となると、この「会社」という存在に不思議な感覚を抱くようになった。
法務局から「登記完了証明書」が届いた日、手元の一枚の紙を見て「これで本当に会社ができたのか?」という違和感を覚えたのだ。
会社とは何か?
- 法的に認められた事業体
- 個人とは別の権利義務の主体
- 「法人格」という目に見えない存在
法的には確かに会社が誕生したのだが、その実感がわかない。
20年以上、起業相談に乗ってきた私でさえ、この感覚に戸惑った。
実感が湧かないまま、銀行口座開設や税務署への届出に向かう道中、自分が何か「ごっこ遊び」をしているような感覚に襲われたものだ。
行政とのやりとりで見えた現場のギャップ
設立直後の会社は、まだ「社会的存在」として認知されていない。
税務署や年金事務所、銀行などとのやりとりで、ようやく「会社」としての輪郭が見えてくる。
しかし、その過程では様々な「現場のギャップ」に直面することになる。
1. 知識と現実のズレ
- 税理士に聞いた手続きが窓口で通用しない
- インターネットで調べた情報と実際の必要書類が異なる
- 窓口ごとに説明や求められる書類が変わる
2. 対応の温度差
- 熱心に相談に乗ってくれる担当者と、事務的に処理する担当者
- 新設会社への不信感が見え隠れする対応
- 「前例がない」と門前払いされるケース
この時初めて気づいたのは、「会社」は単なる法的実体ではなく、社会との関係性の中で少しずつ「実在」するようになるものだということ。
こうした複雑な行政手続きの負担を軽減するために、会社設立を神戸で専門家に依頼することも一つの選択肢だろう。
専門家のサポートがあれば、初めての会社設立でも必要な手続きをスムーズに進められる可能性が高まる。
登記だけで会社ができると思っていた私の認識は、完全な幻想だった。
仲間との温度差に戸惑う瞬間
理想と現実のあいだで揺れるビジョン共有
会社設立前、仲間と何度も語り合ったビジョン。
「こんな会社にしたい」「このような価値を生み出したい」と熱く語り合った夜も数知れない。
しかし、いざ会社が動き始めると、そのビジョンへの温度差が徐々に見えてくる。
同じ言葉で語っていても、各自が描いている未来像は微妙に、時には大きく異なっていたのだ。

この温度差は、特に以下のような場面で顕著に現れた:
- 事業の優先順位をめぐる議論
- 初期投資の額と回収見込みについての考え方
- 「成功」の定義そのもの
- 会社の社会的意義についての捉え方
長野の山奥で始めた地域活性プロジェクトで、ある共同創業者は「地域に根差した持続可能なビジネス」を思い描き、別の創業者は「全国展開の足がかり」と考えていたことが判明したときは、互いに「本当に同じ会社の話をしているのか?」と戸惑ったものだ。
ビジョンの共有は一度きりのイベントではなく、継続的なすり合わせのプロセスであることを、身をもって学んだ。
「責任の所在」が曖昧になる怖さ
会社設立時、最も意識して話し合ったのが「責任分担」だった。
にもかかわらず、実際に事業が動き始めると、思いもよらない「責任の空白地帯」が生まれた。
誰かがリーダーシップをとって決断を下さなければならない場面で、全員が互いの顔を見合わせる。
そこにあるのは、切実な「責任の曖昧さ」だ。
「誰かがやるだろう」から「誰もやらない」へ
会社法上の責任区分と、現場での意思決定の責任は異なる。
法的には代表社員や取締役に責任があっても、実際の業務では判断に迷う場面が数多く発生する。
例えば以下のような状況だ:
1. 契約書の最終確認
- 全員が目を通したが、誰も最終責任者ではない
- 問題発生時の責任の所在が不明確
2. クライアントからのクレーム対応
- 複数メンバーが関わったプロジェクトでの失敗
- 誰が謝罪し、どう対応するかの判断が曖昧
3. 採用の意思決定
- 全員が面接に参加したが、最終判断者が明確でない
- 「皆の総意」という名の無責任な採用決定
会社組織として成熟していくためには、こうした「責任の空白地帯」をなくしていくことが不可欠だ。
しかし、平等な関係を重視する創業期において、これは想像以上に難しい課題だと痛感した。
お金の話になると場が凍る
出資と報酬、誰も口にしたがらない問題
会社設立時、最も気まずい雰囲気になるのが「お金」の話だ。
出資比率や役員報酬について、率直に話し合えない空気が流れる。
なぜなら、そこには創業メンバー同士の「価値」という敏感な問題が潜んでいるからだ。
私たちの場合も例外ではなかった。
会社設立前の打ち合わせで、次のような場面が何度も訪れた:
- 出資比率の提案後に漂う沈黙
- 「報酬はいくらが適切か」という問いに対する曖昧な返答
- 「とりあえず利益が出てから考えよう」という逃避的な合意
- 経費の使用範囲をめぐる微妙な空気
お金の話は、創業チームの価値観を最も鋭く映し出す鏡だ。
特に、異なるバックグラウンドを持つメンバーが集まった場合、「適正な報酬」の感覚にはかなりの開きがある。
大企業出身者にとっての「控えめな報酬」は、個人事業主にとっては「破格の待遇」に感じられるケースもあるのだ。
信頼関係と現実的な取り決めの必要性
「信頼し合っているから細かいことは決めなくていい」。
この考えは、会社設立時の大きな落とし穴になる。
創業期の熱狂の中では「信頼関係さえあればお金の問題は後回し」と考えがちだが、実際にはその逆だ。
信頼関係を長く保つためにこそ、初期段階での明確な金銭的取り決めが不可欠なのだ。
以下の項目については、できるだけ早期に文書化しておくべきだろう:
1. 出資比率と株式(持分)の分配
- 金銭的出資だけでなく、労力や知的財産も評価する方法
- 将来的な株式(持分)の希薄化に関する合意
2. 役員報酬の決定方法
- 固定報酬と変動報酬の割合
- 業績連動の基準値
3. 経費の使用ルール
- 事前承認が必要な金額の基準
- 個人的費用との境界線
4. 利益分配の原則
- 再投資と配当の考え方
- 非常時の報酬カットルール
こうした取り決めは、必ずしも厳格な法的文書である必要はない。
重要なのは、お互いの期待値を「見える化」し、後から「こんなはずじゃなかった」と感じるリスクを減らすことだ。
信頼関係があるからこそ、難しい話題にも正面から向き合う勇気が必要なのだと実感した。
思っていたより「社会的信用」が低い
銀行口座が開けない!?設立直後の壁
会社設立後の最初の関門が「法人口座の開設」だ。
これが予想以上に困難な壁として立ちはだかることを、多くの起業家は知らない。
私も例外ではなかった。
登記完了証明書を手に銀行に向かった私たちを待っていたのは、想像もしていなかった厳しい現実だった。
近年、法人口座開設の審査は厳しくなっており、2018年に金融庁が公表したマネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン以降、金融機関が求める書類が増加し、手続きが複雑化している。
口座開設時に直面した壁は以下のようなものだった:
1. 必要書類の多さと厳格さ
- 登記簿謄本、印鑑証明書だけでは不十分
- 事業計画書や取引先との契約書まで求められる
- 全ての書類が最新のものである必要性
2. 審査の厳しさ
- 新設会社への不信感が前提にある雰囲気
- 「実体のある会社か」を疑う目線
- 何度も同じ質問を繰り返される違和感
3. 待機期間の長さ
- 「審査に2週間〜1ヶ月かかる」という予想外の回答
- その間の資金繰りの困難さ
特に驚いたのは、20年のキャリアを持つ私が代表を務める会社でさえ、社会的信用が低いと見なされ、取引先からも信頼性が低く見られる可能性があることだった。
これは設立したてのベンチャー企業の宿命なのかもしれない。
外からの”見る目”にさらされる感覚
会社を設立すると、これまでとは異なる「目」で見られるようになる。
それは、「個人」ではなく「会社」として評価される目だ。
この視線の変化に、私は大きな違和感を覚えた。
長年培ってきた個人としての信頼や実績が、新設会社という「器」に入った途端に希薄になる感覚。
以下のような場面で、その違和感は顕著だった:
- 取引先との初回商談で感じる警戒心
- クライアントからの「他の実績は?」という質問
- 契約書の細部にわたる厳格なチェック
- 支払い条件での不利な扱い(前払いの要求など)
これは、個人事業主として活動していた頃には感じなかった視線だ。
「会社」という存在は、社会からの信用を一から積み上げていく必要がある。
そして、その過程で創業者自身も「会社の顔」としての自分を意識せざるを得なくなる。
私服で気軽に打ち合わせに行けた相手とも、会社の代表として会うと雰囲気が変わる——そんな微妙な空気感の変化にも敏感になった。
この「見られ方の変化」は、創業者にとって想像以上の心理的負荷となり得ることを、身をもって理解した。
「自分が会社」になる覚悟
代表という立場が突きつけてくるもの
会社の代表になるということは、法的責任を負うことだけではない。
それは「自分自身が会社と同一視される」という、想像以上の精神的負荷を伴うものだ。
私が代表として活動を始めてから気づいたのは、自分の一挙手一投足が会社の評価に直結するという重みだった。
ある日、取引先との打ち合わせで私が軽率な発言をしたことで契約が白紙になりかけた。
その時、「これは水野個人の失敗ではなく、会社の失敗として記録される」という現実に打ちのめされた。
代表者が直面する現実には、以下のようなものがある:
1. 言動の重み付けの変化
- 何気ない発言が「会社の方針」として受け止められる
- 個人的な意見が「会社の見解」に昇格してしまう
2. 責任の際限なさ
- 社員のミスも最終的には代表の責任に
- 「知らなかった」が通用しない厳しさ
3. 孤独な意思決定
- 最終判断を委ねられる重圧
- 「誰にも相談できない」状況の頻発
何より強く感じたのは、個人と会社の境界線の曖昧さだ。
プライベートの時間でさえ、「代表」という肩書から完全に解放されることはない。
この「24時間365日、会社の顔であり続ける」感覚は、創業前には想像もできなかった違和感だった。
肩書ではなく”背中”で語るリーダーシップ
会社設立直後、私は「代表」という肩書に頼ったリーダーシップを試みた。
しかし、それは見事に機能しなかった。
肩書だけでは人は動かないどころか、むしろ反発を生むことを痛感したのだ。
真のリーダーシップは、日々の行動—-いわゆる”背中”で示すものだと気づいたのは、ある失敗がきっかけだった。
締め切り直前のプロジェクトで、私だけが早く帰宅した翌日。
オフィスの空気は明らかに変わっていた。
それからは意識的に、以下のような「背中で語る」リーダーシップを心がけるようになった:
- 朝一番に出社し、最後に帰る
- 自分から率先して嫌な仕事を引き受ける
- 失敗があれば真っ先に自分の責任を認める
- 成功は徹底的にチームの功績として讃える
この「背中で語る」姿勢こそが、形式的な権限以上に組織を動かす力になると実感した。
肩書に頼らないリーダーシップへの転換は、私自身の大きな成長でもあった。
会社が危機に直面したとき、メンバーが私についてきてくれたのは、「代表だから」ではなく「水野だから」という信頼関係があったからこそだ。
その信頼は、日々の小さな「背中」の積み重ねでしか築けないものだった。
まとめ
会社設立という、一見するとシンプルな「法的手続き」。
しかし、実際に自分が当事者として体験してみると、そこには数多くの「違和感」が存在していた。
- 「登記すれば会社」という幻想と、社会との関係の中で徐々に実体化する会社の現実
- 共に船出した仲間との間に生じる微妙な温度差と、責任の所在の曖昧さ
- お金の話題がもたらす空気の凍結と、それでも向き合うべき現実的な取り決めの必要性
- 想像以上に低い「社会的信用」と、一から積み上げていく信頼関係の大切さ
- 「自分が会社」となる覚悟と、肩書ではなく背中で語るリーダーシップの真髄
これらの「違和感」は、決して否定的なものばかりではない。
むしろ、この違和感こそが、個人から法人へ、そして創業者から経営者へと成長するための必要なプロセスだったと思う。
長年、起業支援に携わってきた私だからこそ、この「支援する側」と「される側」の視点の違いを伝えられるのではないかと考えている。
これから会社を設立する方々へ。
法的手続きの先にある「違和感」の存在を知っておくことで、より現実的な覚悟と準備が可能になるだろう。
そして、すでに設立した方々へ。
あなたが感じている「違和感」は、あなただけのものではない。
多くの創業者が直面する普遍的な感覚であり、乗り越えるべき成長の証なのだ。
会社設立は、紙の上の手続きではなく、人間的成長の旅の始まりなのかもしれない。
最終更新日 2025年4月25日